







気が付くと、小学校の正面玄関にクリスマスツリーがキラキラと新鮮に輝いていた。
3年程かけて1800年代後期に設立された小学校のお色直しがようやく終了した様だ。 私の住んでいる住居も、、、というか、この通りは同年代に建設された建造物が並んでいるが、小学校もその中の一つで同じ年代に建てられた。
近年石畳の通りは少なくなっているが、Kielortalleeキールオルトアレーは、つまり @私の通り@ は、昔そのままの石畳、、、ツルツルになった石畳なので滑らないよう歩く、、、これもボケ防止かと、なるべく安全そうな石を選んでゆっくりと歩くが、情緒があり同時にある緊張感が絡まってスリルと情緒とボケ防止を楽しむ。
天候の悪い時は滑らない歩道を歩くように心掛けるが、大概は @危険がいっぱいの石畳を選ぶ@
写真は、我が家、日本式の4階から撮影した小学校正面玄関。

最近、定期に興味をもち、まずはインターネットで下調べをした。 その中でシニア定期が結構手軽な値段であったので、HVVハンブルグ交通協会へ出かけ受付のオジサンに説明を聴き、シニアの最短距離、従って一番格安な定期に決め契約をし、即その契約した定期を使って帰宅した。
それから間もなくして、HVVから手紙を受け取り、契約の際に必要な証明書が欠けていた、、、という趣旨、それでもう一度出かけてみると、、、何と現在は、その、私が求めた格安定期は発行されていないとの事。。。
それでまず、典型的なドイツでの出来事!、、、と、なんだか素直に思ってしまった、、、
すでに契約した時に1か月の料金は支払いしてあるので、、、其の料金は絶対に返してもらわにゃ、、、、と真剣に考えた。 それで、今日の今、ここへ出かける前にもう一度インターネットで調べてきたが、インターネットには、ちゃんと数日前と同じようにこの定期も入っていた、、、と結構キツイ表情と語調で強調した。。。
私の真に迫った迫力が功を奏したのか、或はそういう事になっていたのか、受付のオバちゃんは支払った金額は送金しますと素直に答えた。
考えてみれば、そんな事は当たり前なのに、構えていた私は、、、兎に角戦闘開始姿勢に入って何と言おうかとセリフを考えていた私は、気が抜けてしまった。


まず何を連想したかと問われれば、、、テレビでよく出てくる場面、したたかな刑事が何やら深い瞑想に沈み夜のしじまにとって付けた様な突然の忌々しい事件の謎の前に立っている。。。。。でこのビニールの大きな長い物はテレビの探偵モノで付き物の情景、、、イワユル、テレビで良く聞く!ガイシャ!。。。。。。。。。。。。そんな情景を拡大した様な風景・・・・・だったので、この大きなビ二ールの包が殊の外印象的だった。
これは、そんな恐ろしい物ではなく、早、年の瀬の足音が聞こえウキウキするような、またいつもの事ながら、深い感慨と共に待ちわび、どこか胸がキュ-ンとして一抹のわびしさが重なりあう複雑なそして、、、日本の場合、クリスチャンでもないのにクリスマスといって国じゅうが沸き上がり踊りだし、踊らされる滑稽な年末行事の始まりハジマリーーーーーーー
でこの中身はモミノ木、クリスマスの樅ノ木 。。。多分、、、 夕方、バスに乗ってRathaus市庁舎の近くまで買い物にでかけた。 驚いたことに、既にクリスマスマルクトの店が立派に立ち並んでいた。 そしてこの写真のビニールに保護されたモミノ木が、、、多分モミノ木が、大分早くなった冬のしっとりとした闇の中に無造作に置いてあった。。。。。。
それで、このかなり大きな普通見かけない包を繁華街から逸れた広場とはいえ、全く無邪気と言うか気にかけずゴロンと放り投げた様においてある、、、とってもドイツらしさの一面が滲み出ている様で私の興味を引いた。。。。。。
それにしても、これは、カッセルのいえ、イエ、、ハンブルグのドクメンタ、、、を見つけた



モチロン、第一条件は薄く切る事。
まず、こう言う、、、薄く切って下さい、、、そうすると、、、売り子は、切り始めるが大概の場合は、こちらが希望するほど薄くない、、、ので、もっと薄く切って、、、と注文する、、、それで薄さがOKの場合もあるが、まだまだ希望の薄さに達していない場合は、、、大概の場合、、、兎に角こちらの希望を貫き通す事。。。
@初めに言葉ありき@、、、。なんて有名な格言のように、以心伝心ではなく武器は言葉、、、、、
これはこのドイツ社会というかヨーロッパ一般に通じる事で、お互いの意見、希望それを主張することにより成り立っているので、@お客様は神様@ なんて哲学は辞書には見当たらないので、、、兎に角、自己の意見意志を表言。
はじめに言葉ありき
それで、、、生ハムは兎に角、薄く切らなと美味しさを堪能できない、、、丁度、すき焼きの肉を厚すぎて切った様なものになってしまう。
生ハムにはドイツ製、イタリー、スペイン、ポルトガル、スイス、フランスと様々あるのでそれぞれを試してみるもの生活の変化と楽しみが増す。


昨日は、私が住んでいる地域のマルティン祭の行列の日だった、、、生憎というか、この時期としては普通の天候、、、雨が降ったり止んだり、その上気温は急に下がりだす、、、昨日は日中4度前後、、、そして坂を下るように午後暗くなり始める時間が急さを増す、、、兎に角そんなこの時期としては、普通の夕方に雨も加わり典型的な11月の夕方、、、この写真を撮ったのは、夕方5時ごろ。、、
子供達は、提灯行列の後夫々の地区の小学校に集まり、有名な寸劇、、、ボロをまとった貧しい男にマルティン着ていたマントを半分に切って与えたという有名な話の寸劇の後、提灯をかかげ、近くの商店街、或は住宅街へ出かけ、歌を唄いそのご褒美に持参した袋に菓子類や或は文房具などを入れてもらう、、、住宅街では、それぞれの家庭が用意しておくようだ。 3人の子供達もいつの間にか成長し一人の孫も小学校4年生になり、そろそろそんな事には興味がなくなっているので、最近のトレントみたいなものは皆目見当がつかないが。
長男の時代は、提灯の明りはローソクだったので、時々提灯に火がつき燃えてしまう事があったが、最近は豆電球なのでそんな事もなく快適な提灯行列になったが、ローソクの灯の方がこんな行事、聖マルティンの時代を偲ぶには情緒があるが。。。提灯だけではなく多くの現代の合理的、な生活に当てはまる事ではある。。。。。。。。




ドイツの小学校は4年生で卒業、その後5年生はギュムナジウムか、職業学校となり、9年ある。 ギュムナジウムは新たに1から始まらず、其のまま小学校の続きの5年生となり13年生で卒業となるが、その間落第は付き物で水準に達しない生徒はかなり容赦なく落第というか、やり直し、停年となるか他のギュムナジウムに移る。 ギムナジウム卒業は大学入学許可を意味している。 従って、ギュムナジウムの卒業証書がない限り大学入学は不可能となる。 兎に角、大学進学であろうがなかろうが、職業学校では、中世の徒弟制度の名残の様なマイスター獲得、大学進学コースではギュムナジウム卒業証書なしではドイツ社会では不利になる。

まだ幼さが残っている5年生か6年生

後姿は立派な一人前の女性。。。特にこの年齢の若者は女性らしさを殊更に強調して装っている、見事な曲線美を謳歌している。。。それで私はいつも民族の体形から、外見から根本的に異なっている事を視覚的に理解し、文化の違いの源林の中を通り過ぎる。。。これを、つまり、、、比較文化林


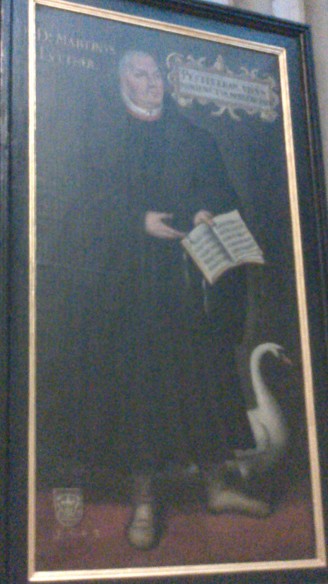
このルターの絵は、カフェ パリー の近くの教会にあり、時々、教会の美しい静寂にひたる。 ルターの勇気、意志、自信、誠意、気概、力にひかれる
今年はルッターの宗教改革5百年記念の年となり、いつもより宗教やルターに関するテーマに接する機会が多い。 視覚から訴えかけてくる本屋さんのウインドウは興味を惹く。 外出時の一つのささやかな楽しみになっている。
ドイツの本屋さんのウインドウは、新書を並べ宣伝、デザインに凝っている印象を受ける、、、限られた分野以外はお手上げの日本人の私にとっても興味をそそり、また見ているだけでも、本の表紙のデサイン、本のタイトル、色彩、、、まずはその全体の構成、、、本屋のウインドウなんてものは、モードの店ではないので、大体そんなに大きくないが、その限られた空間を色彩、遠近感、タイトルが与える空気、印象、心理的影響そこから生まれる興味を惹きだす事にコレ専念している、、、で、楽しい。。。。。それで、ルッターに関する本を4冊買いこんでしまった。
ルッターの肖像画には、時々背景に白鳥が描かれている。。。。。がそれには、こんな理由が。
ルッターの約100年前にルッター同じような理由で教会を批判した牧師がいたが、Johannes Hus ヨハネス フス という牧師は簡単に表現すれば、時期尚早、百年早すぎたために火あぶりの刑で敢え無い最後をとげた、、、と言う事。
それで彼の名前Hus は、ガチョウと言う意味で、彼が教会の意向に反する主張を曲げないので、牢獄に捕えられた時、フスはこう言った 、 奴らが、私を火あぶりにしたら、ガチョウを焼いた事になる、、、でも百年後には白鳥が鳴くのを聴く事になるさ…..神のおぼしめしであろうが、なかろうが! この白鳥はルッターの先駆者Husを象徴しているとの事。
ルターの宗教改革はフスの約百年後で、ルター自身フスの様に火あぶりの刑に処せられるのではないかという恐れはいつもあったという事、、、ただ、丁度、グーテンベアクの印刷技術の発明により、又ルターはラテン語でなく、当時の話言葉で書いたという理由からも一躍彼は当時のメディアの寵児となったとの事、、、そういう事からも教会はルターに手を出す事は不可能であった。
出版社、、、というか当時の出版社のハシリは笑いが止まらなかったというが、それまで出版社という存在はなかった、ルターは一切お金には興味はなく一銭も受け取らなかったという事。
一日と火と\人ひとひとほちほちひとんちまんだらアめん、、、世の中面白いですネー、、いきているのはやめられない